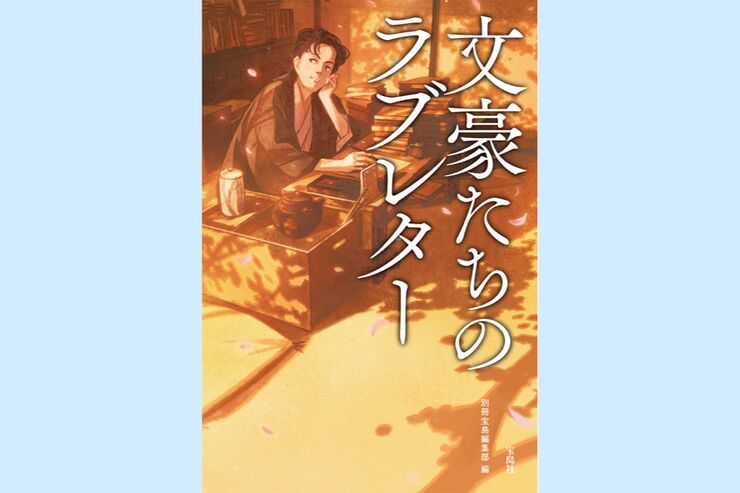「手紙」は、素直に自分の心を書き、相手に送るものです。特に、誰かに自分のことを好きになってもらおうという目的をもって書かれたラブレターには、書く人の人間性がはっきりと表れます。文章を書き、読者に共感を抱かせることを生業としている文豪ともなれば、相手の心をつかんで離さないはず。
本書は、芥川龍之介、石川啄木、国木田独歩、太宰治、夏目漱石、森鴎外など、計19人の文豪たちが綴ったラブレターを集めました。手紙に加え、当時の状況を理解しやすいよう、文豪と恋人・関係者の相関図や解説などを加えて詳しく紹介しています。本書を読むことで文豪たちの人となりに触れ、再度彼らの創作した作品を読んでみると、今までの印象とはまた違った見え方がするかもしれません。今回は、芥川龍之介、太宰治、夏目漱石3人のラブレターについて紹介します。
参考文献:『文豪たちのラブレター』(別冊宝島編集部/宝島社〔2018年9月出版〕)
素直に愛の言葉をしたためた、芥川龍之介
芥川龍之介のラブレターの相手は、8歳年下の塚本文(つかもとふみ)です。彼のラブレターを読む前に、芥川龍之介という人物について簡単にお話しておきましょう。
芥川龍之介は、明治25(1982)年に、東京で生まれました。生後間もない頃に母が体調を崩し、龍之介は母の実家の芥川家に引き取られ、養子になります。龍之介は義父母の期待に応えるために勉学に勤しみ、府立第三中学校に進学。そして、親友の山本喜誉司(やまもときよし)の姪で、まだ8歳の少女であり、後に妻となる塚本文(つかもとふみ)に出会います。その後、東京帝国大学時代に出会った吉田弥生(よしだやよい)と恋に落ち、結婚を考えますが、芥川家の猛反対にあって断念し、彼女は違う人と結婚してしまいます。大きな挫折感を味わった龍之介は小説の執筆に打ち込むようになり、大小4(1910)年に『羅生門』で文壇デビュー。夏目漱石の門下生となって、数々の傑作を生みだしました。
そして龍之介は、美しく成長した文と再会。義父母が結婚相手として文を勧め、当初乗り気ではなかったものの、やがて恋心を持つようになり、婚約時代には慈しみに満ちた手紙を何通も送っています。手紙には、素直な愛情表現だけでなく、彼女を励ます温かい文面もあり、時には泣き言をこぼし、年下の文に甘えることもありました。
龍之介は、結婚前の文に宛てて「この頃ボクは文ちゃんがお菓子なら頭から食べてしまいたい位可愛い気がします。嘘じゃありません。文ちゃんがボクを愛してくれるよりか二倍も三倍もボクの方が愛しているような気がします」と、読んでいるこちらが赤面してしまうような、熱烈な愛の言葉をラブレターにしたためています。
これから約1年半後の大正7年3月12日に文と結婚し、鎌倉で新婚生活を営むことになります。文は龍之介との間に3児をもうけ、次男・多加志(たかし)は学徒出陣で戦死しましたが、長男・比呂志(ひろし)は俳優、三男・也寸志(やすし)は音楽家として活躍しました。
晩年の傑作『斜陽』のモデルとなった令嬢との、切ない恋を綴った、太宰治
太宰治のラブレターの相手として紹介するのは、太田静子(おおたしずこ)という人物です。太宰治が彼女と知り合ったのは、すでに2度の心中未遂の後。すでに津島美智子(つしまみちこ)と結婚し、乱れがちだった私生活は落ち着き、小説家として精力的に作品を執筆していた時期に当たります。
太田静子は大正2年、滋賀県の医師の家系に生まれ、いわゆる深窓の令嬢として育ちましたが、25歳の時に父が死去し、病院を閉鎖した母とともに東京で暮らし始めます。一度結婚するものの娘が生後1か月で亡くなり、結婚2年で離婚して大岡山の実家に戻ることになります。この経験を小説にしようと考えていたころ、太宰の「虚構の彷徨」を読み、その中で描かれている罪の意識に深く共感し、太宰に会いたいと考えるようになります。
太宰に手紙を送り、三鷹の太宰の家を訪れたのが昭和16年。その後、2人の間ではしばらくプラトニックな恋愛が続きますが、昭和18年に戦争によってそれぞれが疎開することになり、離れ離れに。終戦の年の暮れに母を亡くして1人となってしまった静子は、太宰に手紙を出して母の死を伝えたことがきっかけで、再度2人の交流は深まります。
その次の年の昭和21年9月ごろの手紙では、「これから、手紙の差出人の名をかえましょう」と偽名を使うことを提案。妻に見つかることを恐れた太宰の小細工ですが、忍ぶ恋が何ともせつないですね。ちょっと面白いのが、その偽名の付け方です。太宰は同じ手紙で「小田静夫、どうでしょうか。美少年らしい。私は、中村貞子になるつもり。私の中学時代の友人で、中村貞次郎というとても素直ないい性質のひとがいるので、あの人のいい性質にあやかるつもり」と記しています。
偽名を使うことに対して「こんなこと、愚かしくて、いやなんだけれども、ゆだんたいてき。」と書いていますが、そうは言いつつもこの状況を楽しんでいるような気すらします。それから昭和22年2月に太宰は静子の家へ訪れて静子の日記を借り、『斜陽』が生まれます。しかし太宰は、翌年の8月に愛人の山崎富栄(やまざきとみえ)と玉川上水で入水自殺を果たしたのでした。
気むずかしい漱石先生が「恋しい」と書いた、たった一つの手紙
慶応3年、江戸生まれの夏目漱石は、江戸っ子で何かと気むずかしく、夫婦関係においてもその姿勢を崩さなかったと言われています。漱石は、見合いがきっかけで、明治29(1896)年に10歳年下の中根鏡子(なかねきょうこ)と結婚します。新婚早々、漱石は彼女に「俺は学者で勉強をしなければならないのだから、お前なんかにかまっては居られない。それは承知して貰いたい」(夏目鏡子述『漱石の思い出』)と、堂々と関白宣言をするほど。新婚でも連れ立って散歩や買い物をすることも避けていたそうです。また、門下生へ向けた手紙では「夫婦は仲がよくても悪くても問題ない」という考え方を述べており、漱石夫妻は新婚特有の甘い生活は送らなかったようです。
新婚から4年後の明治33年に、漱石は文部省の第1回給費留学生としてロンドンへ行きます。当然、妻へ手紙を送りますが、その内容は「歯並びが悪いから入れ歯にしなさい」「寝坊はよしなさい」など、口うるさいことばかり。しかし、ロンドン滞在4カ月、国を離れて半年が過ぎたころ、極度の精神病に悩まされたことは有名です。その時の手紙は、気むずかしくて真面目な漱石先生らしく、漢字ばかりで少し堅苦しい印象の文体ですが、なにかと弱音を漏らしています。そんな中で書かれたのが、「おれの様な不人情なものでも頻りに御前が恋しい」という言葉です。その後すぐに「是丈(これだけ)は奇特と云って褒めて貰わなければならぬ」と冗談めかしているのですが、この奇特というのは誇張ではありません。実は、現在残されている漱石の2500通を超える書簡の中で、妻に対して「恋しい」と書いているのはこの一通のみと言われているのです。
偏屈な漱石らしくない手紙に、鏡子は「あなたの帰り度(たく)なったの、淋しいの、女房の恋しいなぞとは今迄にないめずらしい事と驚いています」としながらも「しかし私もあなたの事を恋しいと思いつづけている事はまけないつもりです」と返信しています。2016年に放送されたテレビドラマ「夏目漱石の妻」でも描かれた、この夫婦の思わぬ仲睦まじさを感じさせるやり取りと言えるでしょう。
文豪たちのラブレターをのぞいてみると、作品にも通ずる独特の書き方や、文豪たちの人間性などが垣間見えて面白く感じるはずです。興味を持った方は、上記3人の別の手紙や、他の16人の文豪たちのラブレターについても読んでみてください。
宝島社のコメント
手紙を読むことで、作品からは見えてこない文豪たちの人間らしい姿に触れていただければ幸いです。
構成・文:吉成早紀
編集:アプリオ編集部