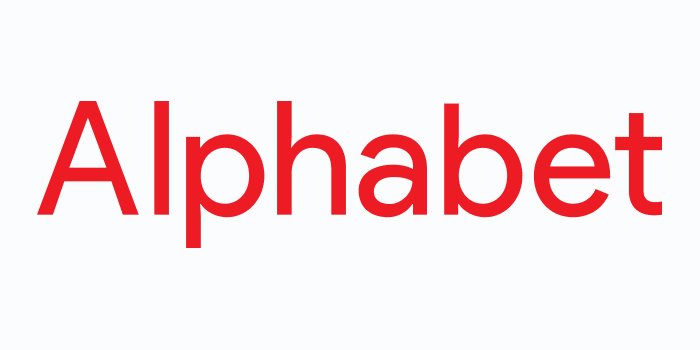
GoogleがAlphabetの子会社になるというニュースは、株式市場では好感を持たれているようです。Googleの株価はAlphabet設立の発表後に、時間後取引で約6%上昇しました。11日も前日比で上昇しています。
Google創業者が新会社「Alphabet」を設立へ、Googleを子会社化
筆者としては予想だにしない出来事だったので、なぜ組織改編をおこなう必要があるのか分からないところがありました。そうして悩んでいるうちに、Googleという企業は優秀な人材の獲得を最重要事項の一つに挙げていたことを思い出し、今回の動きに関連しているのではないかという仮説が浮かびました。特にGoogleが創業期から世界中の頭脳をかき集めてきた経緯を考えると、人の集合体である組織を大きく改編する上で人材の維持・育成の視点は欠かせないからです。
Googleの新しいCEOになるサンダー・ピチャイ(Sundar Pichai)上級副社長は、2014年の段階でGoogleでのかなり多くのサービスを統括していました。それに前後して、ピチャイ上級副社長はMicrosoftのCEOになるのではないかという噂もあがっていましたが、Googleに留まりました。最近では、TwitterからCEOのオファーを受けたのではないか、Googleはそれに対抗する必要があったのではないか、という噂も出ています(下記ツイートは、米雑誌フォーチュンのシニアライターであるMathew Ingram氏のもの)。
Current rumor of the day: Sundar Pichai got offered a CEO job -- probably Twitter -- and Google had to counter somehow
— Mathew Ingram (@mathewi) 2015, 8月 10
そのような情報を追っていくと、今回の組織改編は様々な見方があると思いますが、ピチャイ上級副社長を始めとした優秀な人材がGoogleで仕事を続けるうえで必要な動きでもあったのではないかと考えるようになりました。
Googleをファーストチョイスに
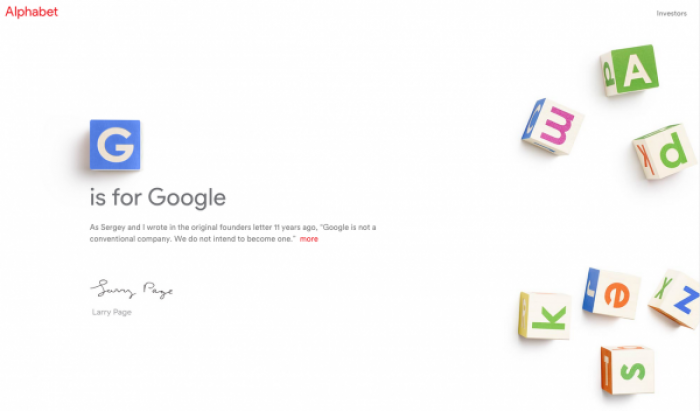
Googleでは今、有能な人材が相次いで離れています。
2014年5月にはGoogle Brainの責任者でスタンフォード大学准教授のアンドリュー・エン(Andrew Ng)氏が、Baidu(百度)設立の新しい研究機関に移りました。7月にはGoogle XのディレクターでGoogle Glassの開発に携わっていたババク・パービズ(Babak Parviz)氏がAmazonに移籍。9月には、Google Xの副社長だったミーガン・スミス(Megan Smith)氏がGoogleを退社し、オバマ政権の最高技術責任者に就任。10月にはAndroid社を創業したアンディ・ルービン(Andy Rubin)氏がGoogleを去りました。
Googleを離れていった人たちにとって確かなのは、Googleがファーストチョイスではなくなったということです。その要因はわかりませんが、人材が流出する状況に対し、Googleは何かしらの対策を講じる必要がありました。それがAlphabet設立、Google、Google X、Calicoなどの子会社化なのでしょう。各企業には経営責任が生まれるものの、意思決定のスピードは速まり、自由度が高まる効果が期待できます。ベストな仕事をする上で、障害が少なくなることは大きな魅力です。そして、Googleを傘下に収めることになるAlphabetは、持株会社として事業全体を緩やかに統括することになります。
一方で、各子会社にCEOを置くことで、ラリー・ペイジ(Larry Page)氏とセルゲイ・ブリン(Sergey Brin)氏には、新たな業務に専念する時間が生まれます。インターネットの会社でありつづけたGoogleの創業者2人にとって、自動運転カーや健康、スマートホーム、人工知能などといった新たな分野への進出を強化し、理想を追求して企業全体の価値を高めていく上で、Google自身が足かせになりつつあったという見方もあります。
後継者を意識する創業者たち
どんなに優秀な人でも「残りの時間」は限られており、ペイジ氏とブリン氏にも、そのときは訪れます。
ペイジ氏は声帯に問題を抱えており、ブリン氏はパーキンソン病になるリスクを高める遺伝子を持っていることを明らかにしています。2人の創業者がGoogleの未来を意識していないというのは、少し考えにくいでしょう。

Googleは優秀な人材を多数抱えている企業なので、タフな組織だとは思いますが、重要ポストを経験することで企業の中枢を担うようになるのはどの企業も変わらないはずです。
CEOや役員などのポストを経験させることで人材を育成していく企業は、日本でも多々みられます。代表例として、20-30歳代のCEOを次々と生み出すサイバーエージェントが筆者の頭に浮かびますが、総合商社(例:三菱商事に所属しながらローソン代表取締役社長になった新浪剛史元CEO)を思い浮かべる人も多いでしょう。
自分たちが築き上げた巨大企業の主要事業や今後伸びていく可能性のある未来の事業の舵取りを任せるに値する人材の獲得と育成は、ペイジ氏とブリン氏にとって急務だったのでしょう。この数年間でピチャイ氏に権限を大幅に委譲してきた事実が、それを裏付けます。
有能な人材は、できるだけの自由と働きに見合う報酬を与えれば必ず結果を出してくる。今回の組織改編は、ただそれだけのことを実行に移すための手段だったのかもしれません。
