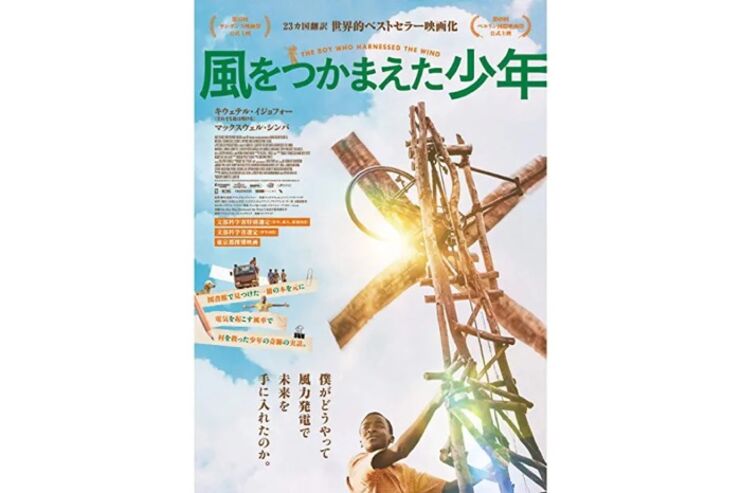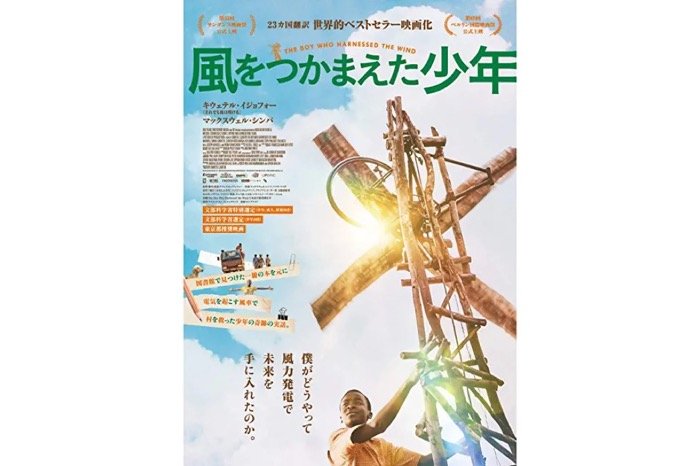
世界最貧国と言われるアフリカ南部の国・マラウイ。映画や小説などの物語でもほとんど描かれることはありません。
そんな、アフリカの小国を舞台した貴重な映画が2019年に日本でも公開された『風をつかまえた少年』です。監督を務めたのは、アカデミー作品賞を受賞した『それでも夜は明ける』の主演・キウェテル・イジョフォー。彼は、2000年代前半、干ばつに苦しむ村を救ったとある少年の話に感銘を受け、映画化を決意し、自ら脚本も書いています。
図書館で独学して風力発電装置を開発
2001年。アメリカ同時多発テロが起きていたころ、アフリカ最貧国のマラウイでは記録的な干ばつに見舞われていました。小さな村に暮らす14歳の少年・ウィリアムは、聡明で学ぶことが大好きな少年でしたが、干ばつによる飢饉の影響で、学費を支払うことができず、学校を追い出されてしまいます。
ウィリアムの姉も大学進学をあきらめざるを得なくなり、恋人と一緒に故郷を離れてしまいます。家族が満足に食べるだけの食糧を確保できず、少しでも食い扶持を減らすためという、家族を想っての行動です。
ウィリアムの父は農業一筋に生きてきて教育を受けておらず、学校にあまり価値を置いていません。さらに、姉の駆け落ちの相手が教師だったこともあり、学校など行かなくてもよいとウィリアムに告げるのです。
しかし、どうしても勉強したいウィリアムは一計を案じ、学校の図書館を使わせてもらうことに成功します。そこで、彼は風力発電についての本に出合います。そして、干ばつに苦しむ家族を助けるために、自ら風力発電装置を作ることを計画するのです。
マラウイでは雨乞いの祈りをささげる伝統があります。ウィリアムの父はこれ以上日照りが続くなら、雨乞いするしかないと言い出す時に、母がそれだけはしないでと言って止めるのが印象的です。ウィリアムの母は非常に進歩的な考えの持ち主で、科学的思考の大切さや勉強の重要性をよくわかっているのです。
ウィリアムの勉強熱心な姿勢は、そんな母の影響なのでしょう。彼は学んだことを見事に実践し、村を救うことに成功します。古い因習にとらわれ、思考停止に陥ることなく、考えて実行すること、そして、そのためには学ぶことが大切を本作は描いています。ウィリアムが風力発電のアイデアを知ったのが図書館であるのも重要な要素です。学びの機会を広く与えることによって、新しい解決策が生まれていくということを示唆しており、教育機会の均等の大切をも訴えています。
なお、本作は実話に基づいていますが、実際のウィリアムも図書館で学んでいました。彼はその後、タイム誌の「世界を変える30人」にも選ばれ、アメリカの名門大学にも通えるようになったそうです。
映画で本当のマラウイを伝えたいという監督の想い
本作の舞台となったマラウイとはどんな国なのでしょうか。
アフリカ南部に位置するこの国は、面積は日本の3分の1ほどで人口は1800万人ほど。公用語は英語とチュワ語で、本作でもその2つの言語が使用されています。
本作で描かれた通り、2001年から2002年にかけてマラウイは、大規模な飢饉に襲われ、2002年には300~3000人が飢えで死亡したという報告もあります。国全体を襲った未曾有の事態から、一つの村を救う偉業だったのですね。
(特活)アフリカ日本協議会:アフリカNOW No.63(2003年発行)
そんな偉業に敬意を表し、マラウイの本当の姿を伝えるために、本作は現地で撮影されました。監督のキウェテル・イジョフォーは、「アフリカで起きていることを、過度にネガティブあるいはポジティブに捉えがちなレンズを通じて伝えるのではなく、もっと事実通りに伝えていく」ことが大切だと語り、メディアに登場するステレオタイプなマラウイとは異なる、実像に迫るアプローチを心がけています。
【単独インタビュー】キウェテル・イジョフォー、初監督作『風をつかまえた少年』に込めた思いとは?(Fan's Voice)
この映画には、学びの大切さがあふれています。社会を変えるのは学び、学んだことを実践する姿勢なのだということを、大変に説得力ある形で見せてくれます。地道な勉強に世の中を変える力があるのです。
動画配信サービスの「Amazonプライム・ビデオ」では、『風をつかまえた少年』が見放題です(2020年12月22日時点)。
構成・文:杉本穂高
編集:アプリオ編集部