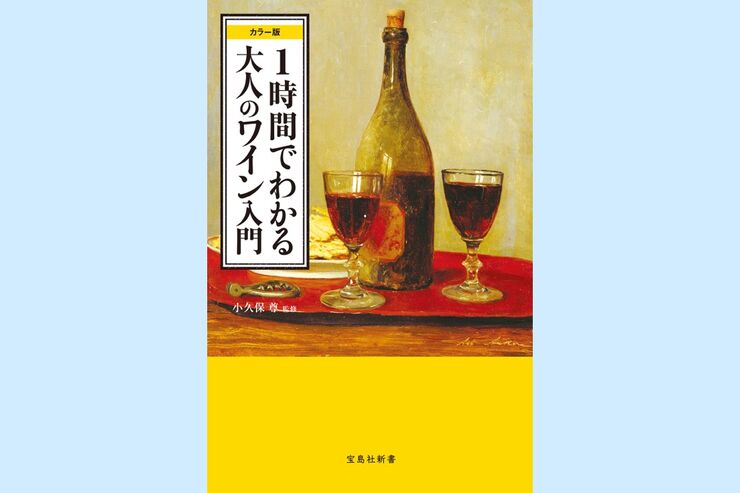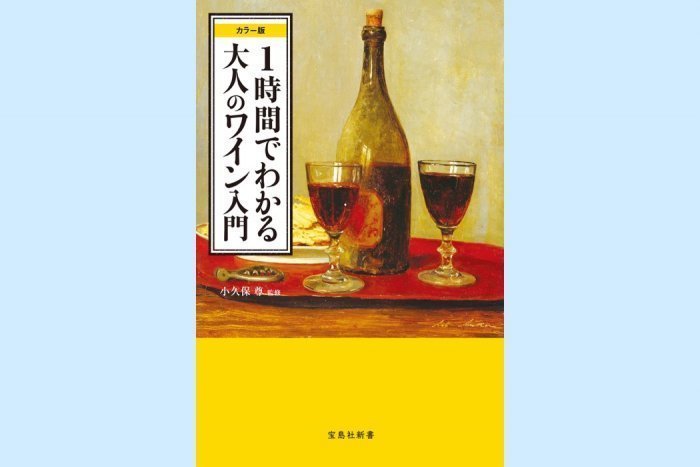
ワインのブームはとどまるところを知らず、昨今ではさらに人気を集めています。香り、味わい、余韻への感想、注目のワイナリーや造り手の情報、醸造されるまでの背景といったワインの話題は、みんなが楽しく盛り上がれる“共通語”にもなるため、基礎知識を知っておきたいという人は多いでしょう。しかし、ワインには奥深い情報が数えきれないほどあり、ソムリエやワインエキスパートなどの資格も人気を博しています。
本書は、ワインの基礎知識を知りたい人たちにおすすめの入門書です。誕生から発展、進化といったワインの歴史だけでなく、伝統国や新興国の特徴やブドウ品種による味わいの違い、テイスティングの意味合いや作法、食事の際に赤・白・ロゼなどどんなワインを選べばよいのかなど、知っておきたい基礎知識を端的にまとめています。
本書を読めば、仲間内での会話だけでなく、ワールドワイドに活躍するビジネスパーソンであればパーティーの席で使えるビジネスツールとして、きっと役に立つはずです。今回は質、量、文化ともに世界をリードするワインの国・フランスをテーマに、フランスワインの歴史や産地別の特徴、味わいについて簡単に紹介します。
参考文献:『カラー版 1時間でわかる大人のワイン入門』(小久保尊著/宝島社新書〔2019年3月出版〕)
「ボルドー」「ブルゴーニュ」「シャンパーニュ」など、フランスワインの歴史と主な産地
「ボルドー」「ブルゴーニュ」「シャンパーニュ」などの単語を聴いたことはないでしょうか。ワインに詳しくなくても聴き馴染みがあるという人が多いこの言葉ですが、実はフランスの地名です。フランスはワインの国とも呼ばれる伝統国。フランスワインを知ることは、ワインそのものへの理解を深めることにつながります。まずは、フランスワインの歴史をたどってみましょう。
ワイン伝統国であるフランスに初めてワインが伝わったのは、紀元前600年頃です。地中海東岸中部に都市国家を築いたフェニキア人が、中東で生まれたワインをフランスのマルセイユに持ち込んだのが始まりといわれています。
その後に侵入した古代ギリシア人によってワイン造りが盛んになり、紀元前1世紀にはローマ帝国の将軍・シーザーによって大規模な遠征が行われ、各地にブドウ栽培とワイン造りが伝えられました。ワイン造りは3世紀頃までに、マルセイユ近辺にあるローヌ川沿岸からボルドー、ブルゴーニュ、ロワール、シャンパーニュと、徐々に北上しながらフランス各地に伝播していきます。そして、キリスト教との結びつきを深めてミサ用のワイン需要が強まり、修道院でもワイン造りが始まるようになりました。
17世紀には「瓶詰め」「コルク栓」が発明され、ワインの流通量は飛躍的に伸び、18世紀には華やかな宮廷文化を彩る価値ある財産として所有欲を掻き立てる存在へと変化して行きます。産業革命によって醸造技術が大きく発展し、厳格な格付けと法整備、造り手たちのプライドなどによって、フランスはワイン王国へと成長しました。
フランスではほぼ全土でワインが生産されていますが、ボルドー、ブルゴーニュ、シャンパーニュはもっとも有名な三大銘醸地といわれています。現在は、個性豊かなローヌやロワールのほか、ロゼで有名なプロヴァンスや、果実味の強い白ワインが主流のアルザスなど、各地で固有のワインが生産されています。
ラベルの読み方は? フランスワインを守る「AOC法」
現在、ワインの生産量ではイタリアが、ブドウの栽培面積ではスペインがそれぞれ1位を誇っていますが、品質の高さやワイン文化、知名度において最も評価が高いのはフランスです。ヨーロッパ各地に広がったワインですが、なぜこれほどフランスで発展したのでしょうか。ワイン用ブドウの栽培に適した気候や風土といった地理的要因や、フランス統治の経緯や背景などの歴史的要因など多数考えられますが、最も大きな要因としていえるのは、フランスが国を挙げてワインの品質とブランド力を守ってきたからです。
ワイン産業を一大産業として考えたフランスは、法律によって厳しく管理するようになります。1905年に生産地名の不当表示を取り締まる法律を、1935年には「AOC法(原産地統制呼称法)」を制定。使用が認められるブドウ品種や栽培方法、収穫量、ワインの醸造法や熟成期間、最低アルコール度数など、細かなルールを産地ごとに決め、これらの条件をクリアしたワインだけがラベルに表示することが許されました。このような、国家主導の厳密な管理によってフランスワインの高品質が維持され、ブランドが守られているのです。
国に認められたワインには、「どの土地の条件をクリアしているか」というAOC表記が認められ、ラベルに「Appellation ○○ Contrôlée」(アペラシオン・○○・コントロレ)と記載することが許されます。この○○の部分には産地(地方、地区、村、畑)が表記されます。
とはいえ、「○○年のワインはいい」「○○年はダメだ」という言葉を耳にしたことがある人も多いと思います。実は、AOCに認定されたブドウ畑の多くは人為的に手を加えることが許されていないため、たとえ雨が少なくても水を撒くことは許されていません。そのため、ワインはその年の気候条件に左右され、出来の良し悪しが発生してしまうです。
かの有名な二大産地、ボルドーとブルゴーニュ
有名なワインの多いフランスですが、フランスワインの双璧といえば、西の「ボルドー」と東の「ブルゴーニュ」です。どちらも最高峰のワインの銘醸地でありながら、両者のワインにはボトルの形や味わいなど、異なる特徴があります。
ボルドーはいかり肩のボトルをしています。赤ワインは重厚でがっしりした味わいで、渋みが強いと言われています。対してブルゴーニュの赤は、軽めでやさしく、エレガントな風味。渋みもやわらかく、酸味があって香りは華やかで複雑だという表現をされます。
ボルドーで栽培されるブドウ品種の「カベルネ・ソーヴィニヨン」は、タンニンが豊富な赤ワインの王道品種です。世界には1つのブドウ品種でワインを造る産地が数多くありますが、ボルドーはブレンドも認められており、ここにメルローやカベルネ・フラン、マルベック、プティ・ヴェルドーの4品種を合わせて、造り手独自の味を生み出しています。また、長期熟成することによってタンニンが柔らかく丸みを帯び、優雅で複雑な味わいを演出するのも特徴です。
一方、ブルゴーニュはなで肩のボトルで、赤ワインの8割はピノ・ノワールという品種のブドウで造られています。同じ品種でも地域や畑、天候、造り手によって仕上がりや味わいが異なり、ブレンドによる調整や安定化ができないため、毎年のリリースが楽しみなワインといえます。
ボルドーは自社畑を持ち、ブドウの栽培からワインの醸造まですべてをおこなう「シャトー」と呼ばれるワイン造りが主流ですが、ブルゴーニュは小規模な「ドメーヌ」やブドウを買い付ける「ネゴシアン」が醸造します。
このように、伝統的に違いの多い産地ですが、極上のワインを生産している点ではどちらも引けをとりません。
ほかにも、産地によって味わいや風味も違ってきます。これを機に、ワインに興味を持った人やもっとワインについて知りたいと思ったら、ぜひ本書を手に取ってみてください。
宝島社のコメント
昨今、スーパーなど小売り店で多種多様な銘柄のワインが取り扱われるようになりましたが、「どういったワインを選んでいいのか基準がわからない」という一般消費者が増加しています。また、ワールドワイドに活躍するビジネスパーソンは、欧米を中心に、パーティーや会食の席で「ワイン」が話題にのぼるケースもあり、雑談でも話題に窮することがないよう、ワインの基礎知識身につけることは、必須といえます。そんな「ワイン通」ではない一般消費者や、ワインの知識を身に付けたいビジネスパーソンにおすすめなのが、読んですぐに役立つ入門者向けの本書です。
本書は、ソムリエであり、ワインバーのオーナーソムリエ兼シェフである監修者が、実際にお客さんと接するなかで「ニーズ」のあるワインを選び、紹介しています。小難しいイメージのあるワインですが、地図を交えながら、国別にみたワインの発展史や産地、ブドウの品種、テイスティングの意味など、ワインに関する最低限の基礎知識をわかりやすく、コンパクトにまとめているので、短時間で学ぶことができます。
教養としてワイン知識を身につける必要に迫られたビジネスパーソンをはじめとして、飲食に興味のあるOL、リタイヤ後の時間を豊かに過ごしたい高齢者にも楽しんで読んでいただけると思います。
ワインは高尚で敷居が高い飲み物などではなく、世界中で親しまれている大衆的な嗜好品です。本書で楽しみながら知識を身につければ、さらにおいしくワインを味わうことができるようになるでしょう。
構成・文:吉成早紀
編集:アプリオ編集部