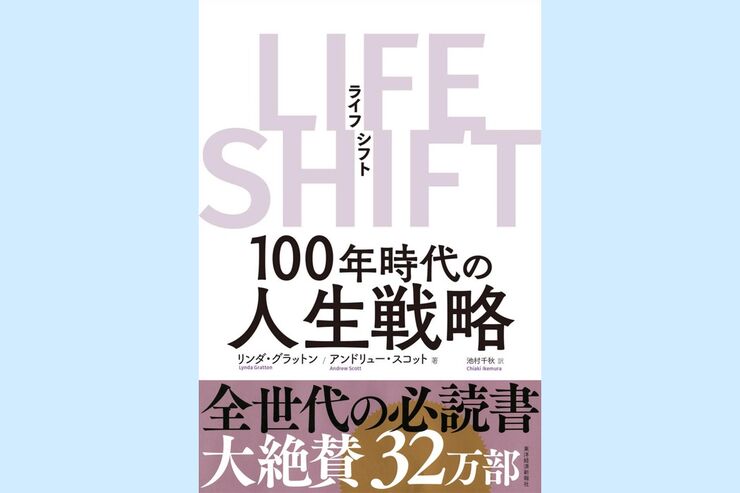人間の寿命は年々伸びていますが、日本に住んでいる私たちは「長寿」と聞くと負の側面をイメージしがちです。定年の高齢化や年金問題といった話題がつきまとい、いつまで働くことになるのか、老後の資金は大丈夫なのかといった不安が頭をよぎります。
そんな中で、今回紹介する『LIFE SHIFT』は、長寿化により訪れる社会や生活の変化を予測するとともに、今生きている人々が考えておきたい対策を提示しています。来たる人生100年時代をポジティブな気持ちで迎えるために、どのように行動するべきかを考えていきましょう。
参考文献:『LIFE SHIFT』(リンダ・グラットン/アンドリュー・スコット著・池村千秋訳/東洋経済新報社〔2016年11月出版〕)
100歳以上生きることを想定する
世界の平均寿命は、右肩上がりに延び続けています。1840年以降、データがある中でもっとも長寿の国の平均寿命をグラフにすると、10年ごとにおよそ2〜3年ずつ平均寿命が延びているそうです。この傾向は先進国だけではありません。1960年、インドの平均寿命は41歳でしたが、2014年には67歳に達しました。国連の予測によると、今後も10年ごとに約2年のペースで延びていくといいます。
世界有数の長寿大国である日本では、100歳を迎えたすべての人に銀杯が送られます。制度が始まった1963年の対象者は153人でしたが、2014年には、2万9350個を突破。2016年以降は予算削減のため、銀杯を純銀製から銀メッキに変更することになりました。私たちが現在の日本の平均寿命である80歳前後を迎える頃には、もっと長生きをするのが当たり前になっているかもしれません。LIFE SHIFTの著者は、本書を読んでいる50歳未満の人は、100歳以上生きる可能性が高いと想定しておいたほうが賢明だと述べています。
「教育」「仕事」「引退」の人生ステージが根本から変わる
これまで、グローバル化とテクノロジーの進化が少しずつ人々の生き方を変えてきたように、長寿化によっても人生のあり方は根本から変わっていくと『LIFE SHIFT』の著者は予測しています。それが「人生のマルチステージ化」です。20世紀には、人生を「教育」「仕事」「引退」の3つのステージに分ける考えが定着しました。生まれてから学校を卒業するまでの教育のステージ、定年まで会社員として労働に従事する仕事のステージ、そして定年後に訪れる老後生活を指す引退のステージです。
今のペースで寿命が延びても働く期間が変わらなければ、長い引退ステージを送るための十分な資金を確保できません。現状の3ステージでこの問題を解消するには、働く年数か収入を増やす必要があります。著者は、100歳まで生きると仮定して、定年後に最終所得の50%相当の資金で毎年暮らすと考える場合は、仕事ステージで毎年10%の所得を貯蓄したとしても、80歳を超えて働く必要があると試算しています。公的年金制度が持続困難になり、受給年齢の引き上げや支給額が削減されるかもしれない日本も、近い将来は、この試算の例外ではなくなるかもしれません。
著者は、100歳を超えて生きる人が珍しくなくなると同時に、現在の3ステージ時代は終わりを迎えるといいます。同時に、人々は新しいステージを人生に追加するようになると話し、いくつかの例を紹介しています。
ひとつは、「インディペンデント・プロデューサー」と名付け、フルタイムで働く会社員の道から外れて自分のビジネスを始める人が突入するステージとしています。インディペンデント・プロデューサーのステージを選ぶ人は、基本的に何代も続く大企業を作ろうとは思っておらず、一時的、あるいはトレンドに合わせた一回限りのビジネスを立ち上げて収入を得ることを目的としています。活動内容は、製品の開発やサービス提供など、取り組む人によって千差万別です。今は、役立つアプリを開発したり、YouTubeなどを通じて価値のある情報やエンターテイメントを提供することで、生計を立てている人もいます。テクノロジーの進歩やプラットフォームの登場によって、活動方法が多様化しているのです。
また、さまざまな仕事や活動に同時並行で携わる「ポートフォリオ・ワーカー」と呼ばれるステージを経験する人も出てくると話しています。これまで多くの人は、仕事ステージにおいて、一企業あるいは一つの職に従事して定年を迎えてきましたが、過去の経験や人的ネットワークを生かして、複数のコミュニティや企業に所属し、複数の仕事に従事する道を模索するようになるといいます。当然、国も新しいステージの登場に合わせて、制度を整えるべきだと著者は述べています。日本では「副業」という言葉が馴染み深いかもしれません。収入やスキルアップなど理由はさまざまですが、望む望まざるに関わらず、会社の外にあたらしい仕事先を求める人は増えています。
紹介した新しいステージの特徴は、特定の年齢層と結びついていないことです。例えば、従来の「教育」ステージであれば、一般的に大学を卒業する20歳代前半までの人を思い浮かべると思います。また、「引退」ステージは定年を迎える60〜65歳以上の人生をイメージするのではないでしょうか。
しかし、例えば「インディペンデント・プロデューサー」であれば、年齢を問わず始められます。これまでは、大学を卒業したらそのまま企業に就職するのが一般的なルートでしたが、現在は就職活動に参加せず、在学中や卒業後すぐに独立してサービスを立ち上げる人もいます。また、一部の国では、学校卒業後の一定期間を長期の旅行やボランティアに当てて自分の進む道を見つめ直す「ギャップイヤー」と呼ばれる期間が存在するなど、選択肢が増えているのです。
もちろん、アイデアや実行力があれば、40歳代の仕事ステージや60歳代の引退ステージからでも、「インディペンデント・プロデューサー」に移行することは可能です。調査によると、起業家全体に占める55歳以上の割合は、1996年が15%だったのに対して、2014年は26%に増加しました。将来は70歳代や80歳代の人が起業する割合も増えると予測しています。今は80歳代の人を見ると、起業するようなエネルギーがある人は少ないように思いますが、長寿になるということは、元気に生活できる期間も延びることを意味しています。将来は、80歳代でも今の60歳代と変わらず働く人が増えていくのです。
著者は、100年という長寿の時代に、従来の3ステージ生活では考えていたライフプランが立ち行かないと考えた結果、新しいステージへ移行していく人が増えると予測しています。そして、国家がかつて、3ステージの生き方を元に、義務教育や採用制度、老後保障の整備などに力を入れてきたように、新しいライフスタイルに合わせた制度を少しずつ整備していくと考えています。
無形資産への投資が重要
紹介しているステージはあくまでも著者の予測ですが、現状の3ステージから外れて他のステージを経験する人は今後も増えていく可能性が高いとしています。長寿化するにつれて登場する人生の新たなステージで能動的に活動するには、変化を受け入れて、新しいスキルの習得に投資する必要があります。その上で重要になるのが、「無形資産」という要素です。無形の資産はお金として何かと交換できるわけではありませんが、仕事などにつながり、有形の資産を形成するという点では無視できない存在です。より良い人生を送る上では、金銭面だけでなく、無形の資産も充実させる必要があります。
『LIFE SHIFT』では、無形資産を次の3つのカテゴリーに分類しています。この無形資産についても、有形資産と同様、意識的に築いていくことが大切です。
生産性資産
仕事の生産性を高め、所得とキャリアの見通しを向上させるために役立つ資産と定義しています。また、このカテゴリーは人生の幸福感全般を高めるためにも非常に重要です。具体的な項目は、「スキルと知識」「仲間」「評判」です。仲間などは一見関係ないようにも思えますが、仕事をする上では、周囲の人との人間関係やチームとしての取り組み方が非常に重要です。また、新しい知識の習得や仲間との関係づくりには、ときにお金をかける必要があるかもしれません。
活力資産
肉体的、精神的健康と心理的幸福感は重要な無形の資産であり「活力資産」と本書では定義しています。具体的な項目として、「健康」「バランスの取れた生活」を挙げています。例えば、肉体だけでなく脳の健康も重要です。脳の機能低下を避けるためには適切な食生活を意識して運動を習慣づけることも大切で、無形資産への投資の一環であると本書では述べています。また、活力資産にもしっかり投資することが、変化を前向きに受け入れるエネルギーになるといいます。
変身資産
変身資産とは、新しいステージへの移行を成功させる意思と能力のことです。3ステージの人生モデルが崩壊すれば、途中で「インディペンデント・プロデューサー」のような新しいステージへ移行する可能性も出てきます。その際に必要になる変身資産が「自分についての知識」「新しい経験に対して開かれた姿勢」「多様性に富んだネットワーク」です。
「自分についての知識」とは自分が好むことや嫌いなこと、アイデンティティなど、自身の内面をよく理解することです。寿命が延びると、国の制度変更や転職、引越しといったさまざまな要因により慌ただしい日々を強いられることになりますが、自分を理解している人は、人生に意味と一貫性を持たせる道を選びやすいので、人生の新しいステージで成功する確率が高く、変化によってアイデンティティが脅かされることはないといいます。「多様性に富んだネットワーク」とは、新しい人生の価値観に触れられる人や、自分が移行したいステージですでに活躍している人と交流して関係を築くことです。すでに新しいステージにいる人も、当初は自分と同じような不安を味わっていた可能性があります。そうした人と触れ合うことが、新しいステージへ移行する抵抗感を乗り越える力になります。
著者は、現在定着している3ステージの概念から脱却して、新しいステージに目を向ければ、働くことがだいぶ魅力的に見えてくると話します。そのためには、貯蓄や給料以外の無形資産にも目を向けて育てることが重要で、今後訪れるであろう変化にもポジティブに対応できるようになるのです。
東洋経済新報社のコメント
日本は世界でも有数の長寿大国で、人生100年時代へ世界に先駆けて突入する国になるでしょう。国連の推計によると、2050年までに日本の100歳以上人口は100万人を突破する見込みです。
100歳まで生きる = 働かなければいけない期間が延びると考えたり、年金制度が崩壊するかもしれないと考えると、将来が不安になったりネガティブな気持ちになる人もいるかもしれませんが、本書でも述べている通り、『LIFE SHIFT』は、長寿の恩恵を受けるための手助けになる本です。読んでいただくと、私たちが迎える人生100年時代に対して必要な準備がわかったり新しい発見があると思います。
構成・文:藤原達矢
編集:アプリオ編集部