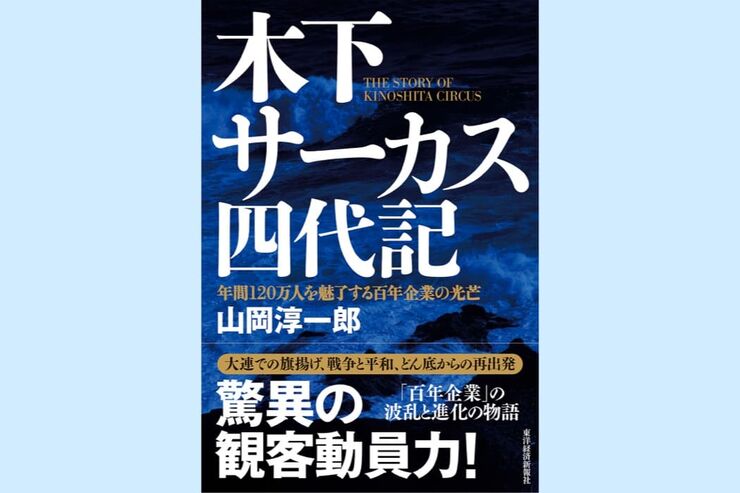木下サーカスをご存知でしょうか。年間120万人の観客動員数を誇る世界のサーカス界で1、2位を争うほどの大サーカス。「宝塚」で有名な歌劇団の本拠地である「宝塚大劇場」の年間入場者数は119万なので、同等と言えるでしょう。ダルビッシュ有や大谷翔平などのスター選手を輩出した北海道日本ハムファイターズは年間200万人の観客動員数なので、木下サーカスの奮闘ぶりが伺えます。
驚きなのが、人気歌劇団やプロ野球チームが常設の場を持つのに対し、木下サーカスは移動先の広場で講演を行い、仮設劇場や団員の住むコンテナハウス、動物の飼育スペース、事務所など約1万坪の土地を手配して営業を行う点です。100人近い団員とその家族で構成される、まるで大家族のような木下サーカスは、どのような共同体で、どうやって大家族的集団を維持しているのか、世界のトップ級サーカスになる秘訣は何だったのか。本書は、そんな思いを抱いた著者が、木下サーカスの巡業に1年間密着し、木下家四代にわたる経営者の軌跡をたどった1冊です。旅興行を実業に変えた執念と、波乱に富んだ歴史が浮かび上がって見えてきます。
参考文献:『木下サーカス四代記 年間120万人を魅了する百年企業の光芒』(山岡淳一郎著/東洋経済新報社出版社〔2019年1月出版〕)
「木下サーカスの四代記
初代に当たるのは、木下唯助(きのしたただすけ)という人物です。1882年に現・丸亀市に生まれた彼は、幼少のころから叔父が率いる動物見世物の一団に加わっていました。23歳の時に、興行師の木下藤十郎の養子に入り、軽業一座を結成して1902年にダルニー(のちの大連)で旗揚げをしたのが、木下サーカスの創業とされています。
プレーイング・マネージャーとして中国のハルビンや奉天、ロシアのハバロフスクやウラジオストク、朝鮮、台湾を巡り、戦前、戦中にかけて岡山の表町の天瀬に映画館や旅館、大衆浴場、料理屋などをいくつも建設するなど実業の才能も発揮。木下サーカスの礎は彼によって築かれましたが、太平洋戦争の空襲によって岡山市街が焼け、サーカスの再興も断念せざるを得なくなります。
そこで立ち上がったのが、娘婿で、事業を継いで二代目となる光三(みつぞう)です。彼は、中国の山西省で特務機関に配属され、現地で銃撃戦に遭い、瀕死の重傷を負うなど戦争経験の持ち主。この体験がきっかけで出会った外務省や出版業界の戦友の人脈を生かし、「サーカスに国境はない」をモットーに、反日感情の激しい東南アジアや、政治的に微妙な関係にある韓国や中国などでも公演を行いました。その後、仮設劇場からテントでの公演へと興業のしくみを転換する革命を起こし、全国各地の地方紙やテレビ局との提携網を構築するなど、近代化に伴うビジネスの原型を構築しました。

2018(平成30)年2月、沖縄・豊見城公演後の場越し
初代の創業、二代目の発展を経て、三代目に就任したのは、二代目光三の息子である光宣。彼はサーカスと演劇を融合させた「神戸ポートアイランド博覧会」を大成功させ、団員の生活環境を向上させるなどの改革をしました。しかし、興行をするも赤字が膨らみ、挽回に奔走するも病気により他界。急遽、次男の唯志が四代目社長に就任し、債務額10億円を10年で完済し、年間観客動員数120万人を記録するほどまでに成長しました。
「四代目社長が考える経営の本質、「一場所、二根、三ネタ」
四代にわたる百余年の木下サーカスの軌跡を取材した筆者は、「つくづく『家族は経営の母体』だと思う」と述べています。創業者一族が経営を担うファミリービジネスは、一見時代遅れのようですが、日本の法人企業の約250万社の97%は同族企業です。日本経済の50%以上の価値をファミリービジネスが想像しているとも言われます。ファミリービジネスには、閉鎖的で人材に乏しい反面、経営判断が早く、長期思考で継続性に優れるという利点があります。
どんな会社にも一長一短はありますが、大事なのは、代々伝わる経営の本質論です。事業を守るためには絶えず変化しなければなりませんが、変えてはならない核心があります。それが経営の本質です。木下サーカスの経営の本質から、驚異の観客動員力の秘密を探ってみましょう。

東京・後楽園球場で開かれた木下大サーカス(1976〔昭和51〕年)
「一場所、二根、三ネタ」。これが木下家に伝わる経営の本質です。「場所」は公演地の選定であり、公園の現場。「根」は営業の根気を、「ネタ」は演目を指しています。木下家では、この3つを磨くように言い伝えられてきました。
特に場所の良し悪しは売り上げに大きく響く重要なポイント。戦後、サーカスや見世物の興行主は仮設興行協同組合を結成して、どのサーカスがいつ、どこを回るかなどを、全国に張り巡らされたネットワークを使ってコースが重ならないように、互いの年間巡業工程を調整していました。しかし、高度経済成長に伴ってテレビなどの娯楽が増えたことで、サーカス団の経営は追いつめられ、仮設工業組合は休眠へと追い込まることに。さらに、都市の空き地が消えて公演用の広場の確保が難しくなるという問題も。彼は、全国の空き地を探し回り、政府の国土計画や都市政策の転換で生じた隙間に着眼しました。民営化に伴って駅周辺と一体的に再開発する計画が実行されるまでに時間がかかり、一時的に生まれた駅周辺の広場を利用することを思いついたのです。
JR東日本と営団地下鉄(現・東京メトロ)の乗り家駅である南千住は、1日の平均乗車人数が2万人を超える、滞在顧客に十分な見込みのある土地。また、福祉施設を利用している障がい者1万人の招待を申し出ることで、行政にとって手薄な福祉事業への支援や集客による地域経済の活性化が魅力的なものとして、荒川区は申し出を快諾したのでした。
しかし、南千住駅があったあたりは、江戸時代から明治時代にかけて小塚原刑場が置かれ、磔、火あぶり、獄門が執行されるなど、権を担ぐ興行界は避けたがる場所でした。南には山谷のドヤ街が広がり、一般客は敬遠気味で、土地の来歴は侮れないとの教訓を学んだそうです。
場所取りの重要性を痛感した「鶴見緑地花博覧会場跡地」の公演

熊本での木下大サーカス公演(2017〔平成29〕年) 撮影:尾形文繁
負債10億円の逆転ののろしを上げ始めたのは、大阪市、鶴見緑地花博覧会場跡地の公演です。「国際花と緑の博覧会」は、90年の春から秋にかけて開かれ、総来場者数2312万6934人と博覧会史上最高の数値を記録しています。大阪市は、その跡地を「花博記念公園鶴見緑地」と名付け、環境を整えて無料で開放しており、植栽に力を入れていましたが、来場者数はまばらでした。もう一度市民を呼び戻したいとの願いから、大阪市のほうから木下サーカスに打診があり、公演を決意。92年3月に公園の幕が上がると、連日満員で、花博の余韻も手伝ってかふた月で約38万人が押し寄せるほど大盛況でした。このことにより、場所の重要さを再認識することになったのです。
ただ、いい候補地を見つけたらすべてがうまくいくというわけではありません。「サーカスが来たら獣のにおいがする。もし猛獣が逃げたらどうするのか、命の補償をしてくれるのか」「観客が集まったら騒ぐし、ゴミがたくさん出るからよそでやってほしい」「静かな生活を乱さないで欲しい」と反対意見が地元住民から出ることで、交渉が難航することも。通常であれば公演地を絞るとその土地の所有者や自治体、警察、消防、保健所などの公的機関の許可を得て住民へ説明に赴き、了解を取り付けます。ところが、大阪府堺市では住民パワーが強く、住民が認めないと行政も認められないというパターンになることも。なぜ反対するのか、その理由をよく聞く努力をし、住民の本音を聞き出すなどして、ようやく了解されたということもありました。
このように、木下サーカスの経営では、「一場所、二根、三ネタ」の精神が息づき、数々の成功を支えているのです。
東洋経済新報社のコメント
3月11日までは大阪うめきた公演、3月23日からは名古屋公演・・・・・・と、年に4~5カ所の旅興行を続け、年間120万人(宝塚大劇場に匹敵)を集客している木下サーカス。
著者の山岡淳一郎さんは、小学生のころに見た木下サーカスが、いまもテント興行を続け、驚異的な集客力を保っていると人づてに聞き、興味をそそられたそうです。
サーカスに古い哀調を重ねていた山岡氏は、取材で公演地を訪ね、固定観念を覆されました。まず、明るい、ショーはスピーディーで圧倒される。「一場所(公演地)、二根(営業の根気)、三ネタ(演目)」を経営の三本柱に、一般企業には想像もつかないビジネスモデルを構築している。
団員たちが寝泊りするコンテナへの宿泊体験も含めて1年間の密着取材で、百年企業の歴史と経営の常道、そして木下家四代とサーカスに集まり、サーカスでつながる人々の人間ドラマが見事に描かれています。
構成・文:吉成早紀
編集:アプリオ編集部