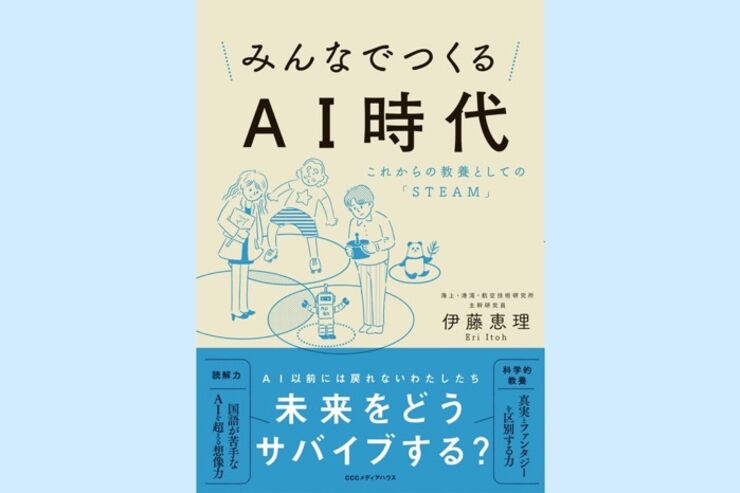現代社会では、ほとんどの人が何らかの形でAIに関わっているのではないでしょうか。毎日使っているスマホを始め、ロボットや車など多くの製品でAIが利用されるようになり、私たちの生活はどんどん便利になっています。
一方で、AIの進化は、ネガティブ論とセットで語られることも珍しくありません。AIの素晴らしい処理能力や判断スピードを目の当たりにすると、「仕事が奪われる」「人間の存在意義がなくなる」といったように、つい悲観的な未来をイメージしてしまいがち。実際、AI研究者の中には、将来消えてしまう職業を真剣に予測している人もいます。
果たして、人類の仕事や存在意義はAIの進化によって脅かされてしまうのでしょうか。その答えに対して、本書『みんなでつくるAI時代』の著者である伊藤恵理さんは、これからの社会システムを作っていく私たち次第で避けることは可能で、一人ひとりが時代にあった科学リテラシーを身につけることが大切と話します。
参考文献:みんなでつくるAI時代 これからの教養としての「STEAM」(伊藤恵理/CCCメディアハウス〔2018年3月出版〕)
AIが進歩した先は、「不老不死」or「人類滅亡」?
AIによって私たちの生活は十分便利になっていますが、まだまだ大きな可能性を秘めており、世界中の技術者が日々研究開発を進めています。
そんなAIの進化について触れる際、しばし議論になるのが「シンギュラリティに到達するか」というテーマ。AIについて解説するテレビ番組やニュースなどで、目にしたことがある方もいるのではないでしょうか。シンギュラリティは、日本語で「技術的特異点」と訳され、テクノロジーが急速に進化し、人間の生活が後戻りできなくなるほど甚大な影響を及ぼす技術的革新を意味します。
しかし、人類はこれまでも多くの技術的革新を経験しているはずです。例えば、スマホやSNSなど、一つの製品やサービスをきっかけに、それらがなかった時代を思い出せないくらい世界が大きく変わる体験を私たちは重ねてきました。では、なぜAIにおけるシンギュラリティが今騒がれているのでしょうか。その理由の一つは、AIが指数関数的に早いペースで成長しており、今以上にさまざまなビジネスを生み出すと期待されているからです。
シンギュラリティ到達後に訪れる世界について、壮大な未来図を描く人物もいます。その一人が、現在Google社でAIの技術責任者を務め、シンギュラリティという言葉を提唱したレイ・カーツワイル氏です。
彼は環境や仕事など、さまざまな分野の変化について予測を立てていますが、特に注目を集めているのが「人間は不老不死になる」というもの。将来は、何十億ものナノマシンが人間の体に入り込み、病原体の破壊やDNAエラーの修復、毒素の排出などをすることにより、人間は老化することなく永遠に生きられるようになるというのです。現在の社会では考えられない未来ですが、本人はいたって大真面目。時期についても、シンギュラリティは2045年に訪れると予測しており、賛同する研究者も多くいます。
一方で、人間の予想を超えるスピードで進化するAIに警鐘を鳴らす人物も。理論物理学者のスティーヴン・ホーキング博士は、AIが人類の脅威になると悲観論を唱えます。将来的にはAIが人間の能力を追い越し、人類を置き去りにして地球の未来の在り方を定義するようになる。その結果、AIは人間を無用の長物とみなし、人類を滅亡させるというシナリオを描いているそうです。将来は映画『ターミネーター』のような世界が訪れるのでしょうか。
無用な不安に煽られないためには
AIによる時代の変化を探るには、「科学技術がどんどん進化したらこんな未来がやってくる」という科学技術を中心とした視点と、「未来の社会を作るためにどのような科学技術が必要か」という社会デザインを中心とした視点は、分けて考える必要があります。たとえ、AIがものすごいスピードで進化しても、同じ時間軸で社会が変わるとは限らないのです。
「AIに仕事が奪われる」という話も衝撃的ですが、本当でしょうか。オックスフォード大学でAI研究に携わるマイケル・オズボーン博士らが2013年に発表した論文には、10年後になくなる仕事がランキング形式で掲載され、1位は小売店販売員となっています。それから5年後の2018年現在、インターネットで求人情報を検索しても大きな変化は特に感じられません。無人コンビニなども登場し、小売店販売員がいない店舗運営も技術的には可能なのかもしれませんが、すぐに取って代わられる心配はなさそうです。
もちろん、技術の進歩によって消えていった仕事はこれまでも存在します。可能性の話をするなら、シンギュラリティによって人類が滅亡するシナリオもあるのかもしれません。しかし、今を生きる私たちがどのような社会を作りたいかを考え、行動することで、不幸な予測を回避するための未来社会をデザインすることは可能です。「ターミネーターは作れる」かもしれませんが、その前に「私たちが実現したい豊かな未来社会でターミネーターを作る必要はあるか」を判断し、選択することができるのです。
大切なのは、未来の科学技術に無用な不安を煽られて「テクノ・パニック」を起こさないこと。科学技術をセンセーショナルに演出して根拠のない話で不安を煽り、利益を得ようとする人やコミュニティも存在します。そのような話に惑わされないためには、「科学の裏付けがあるか?」という一つの指針を持つと生きやすくなるでしょう。
情報を受け取ったら感情的に反応するのではなく、対象の本質を見通し、独自の解決法を探し出す能力は、科学する行為を通して養うことができます。科学とは、まず常識を疑うことからはじまります。科学的な思考方法は、現代のビジネスパーソンが身につけるべきサバイバル術なのです。
AI時代に必要な教養とは?
オズボーン博士らが、10年後に消えて無くなる職業を発表する一方、2015年の3月には、WIRED誌が「記憶の演出家(人生最良の記憶を再体験させる仕事)」や「ロボット・アドバイザー(ロボットにニーズを教育する仕事)」など、2030年にAIやロボットに奪われない8つの仕事を掲載しました。これらを消えて無くなる仕事と合わせて比較すると、AI時代に必要とされる人材は、以下の通りにまとめられます。
- 社会のニーズと科学技術をつなぐ仕事ができる人
- 物事の本質を分析する仕事ができる人
- 世界を舞台にコミュニケーションする仕事ができる人
例えば、「社会のニーズと科学技術をつなげる仕事」として考えられるロボット・アドバイザーであれば、社会のニーズに敏感なだけでなく、法律や規範など社会の仕組みも知る必要があります。さらに、コンピューターに仕事をさせるスキルも欠かせません。要するに、AI時代に必要な仕事には、文系の知識と理系分野の教養が求められます。そんな人材になるために必要なスキルは以下の5つです。
- STEAMの教養
- 社会の仕組みについての知識
- 科学的な思考方法
- 目先(本質を見通す先見の明)・口先(コミュニケーション能力)・手先(論文執筆やプログラムなど手を動かす作業)・胸先(モチベーションや度胸)
- 想像力
「STEAM」とは、ハイテク職種に就くアメリカの人材を育成するために考えられた教育方法で、「科学(Science)」「技術(Technology)」「工学(Engineering)」「芸術(Art)」「数学(Mathematics)」の頭文字をつなげています。
1分野を単独で見るのではなく、他の4分野との関連性を意識することが、テクノロジーが進歩した現代社会では重要とされています。科学や技術と聞くと敷居は高そうですが、STEAMの教養は、本を読むだけでなく、TEDを見たり、科学博物館などに足を運んでみたりすることでも身につきます。また、最新のガジェットやアプリといった、STEAMを社会につなげる製品やサービスを敬遠せず、積極的に試してみることも大切です。その際も単に触るのではなく、機能やデザイン、使い勝手などを意識して見るようにしましょう。
STEAMに関する事柄や新製品などを判断する際の科学的思考方法は、対象を7つの軸で評価する訓練を積むことで養うことができます。
- 先進性 = そのアイデアは過去になかったか? 誰かのマネではないか?
- 機能性 = それは、何かを可能にするのか? これまではできなかったのか?
- 効能性 = それは、必要なことなのか? それは人を幸せにするのか?
- 普遍性 = それは、問題の背後にある未知の何かを明らかにするのか? 何かを予測するのか?
- 目的性 = それは、目的にかなった方法か? こじつけではないのか?
- 唯一性 = それ以外に方法がないのか? ないとすれば、なぜなのか?
- 審美性 = それは、美しいか?
7つの軸は、長崎県立大学の金谷一朗先生がまとめた内容を活用しています。
遭遇したことのない事象に対して狼狽せず冷静に評価するには、この評価軸に立ち返って考えるようにしましょう。正しく評価する能力は、自分のビジネスを客観的に見る際にも役立ちます。
CCCメディアハウスのコメント
各国の研究機関や企業など、さまざまな立場からの意見や利害が絡むプロジェクトを着地点に漕ぎつけるためには、タフな精神力とスマートな交渉力が必要です。
伊藤恵理さんは、「空はひとつ」を自らのモットーに、多くの国際プロジェクトで責任ある立場を任されているかっこいい研究者。
彼女の実体験を読めば、これからはいかにSTEAMの教養が重要であるかがご理解いただけると思います。
構成・文:藤原達矢
編集:アプリオ編集部