
Googleは13日、YouTubeのライブ配信機能である「YouTubeライブ」を全ての一般ユーザ向けに公開した。今後数週間にわたって順次サービスをロールアウトしていく。
ライブ配信機能の利用可否は、YouTubeのチャンネル設定で確認することができる。
YouTubeのライブ配信といえば、国内では2012年6月6日に配信されたAKB48第4回選抜総選挙の生放送が印象的だ。

Googleが、Google+のプロモーションにAKB48を使っていることもあり、ライブ配信の大々的な宣伝が行われた結果、ライブ配信の視聴回数は300万回超を達成した。
現在でも、このAKB48の事例のように、YouTubeライブが活用される場面を見かけるようになってきている。ただし、それは一部の企業レベルに留まるもので、一般個人がライブ配信機能を利用することは原則として許されていなかった(2013年夏から登録者数100人以上のチャンネルで可能)。
どうなる?ニコ生とUstream
本日から一般ユーザでも、YouTubeという世界最強の動画コミュニティで生放送を行うことができるようになったわけだが、そうなると脳裏に浮かんでしまうのは「ニコニコ生放送(ニコ生)」と「Ustream」という競合サービス大手の存在と、その行く末だ。
ニコ生とUstreamでは明暗が分かれるのではないかと、筆者は考えている。
![]()
まず、ニコ生だが、YouTubeライブの影響を受けるものの、大打撃を受けることはないのではないか。
ニコ生は、動画中をコメントが流れていくコメントシステムとサービス開始以来築き上げてきたユーザコミュニティに支えられた独自の文化圏を生み出している。そのため、ライブ配信という点ではYouTube ライブと直接競合するものの、今後もうまく住み分けしていくことができるように思える。
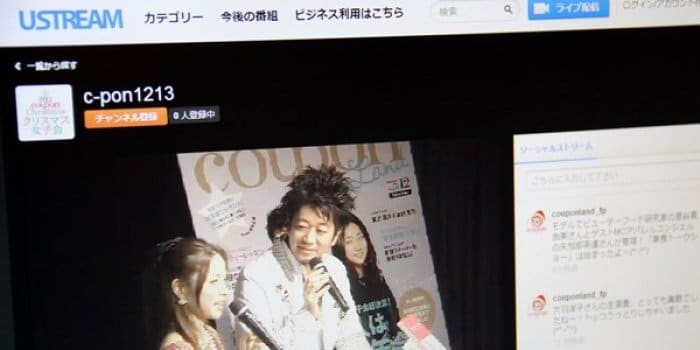
一方、Ustreamには、YouTubeライブと比較したときに見えてくる「強み」がはっきりしない。
Ustreamのコメントシステムは人気を博しているようだが、YouTubeライブにもライブコメント機能が用意されている。UstreamのコメントシステムがYouTubeライブと明確に異なるのは、Twitter・Facebookと連携しているという点。ただ、それゆえにUstreamを使いたいというユーザがどれだけいるかと言えば、少し疑問が残る。
Ustreamと日本語版を提供するUstream Asiaには、ソフトバンク資本が入っている。ソフトバンクの孫正義氏が何らかの手を打ってくる可能性もある。
Google先生によるYouTubeライブがどの程度流行るのか。そして、ニコ生やUstreamなどの競合サービスはこの先、生き残ることができるのだろうか。
